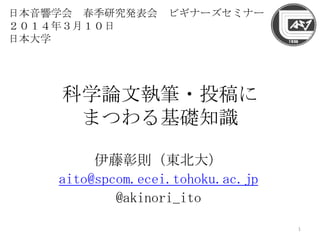科学论文执笔?投稿にまつわる基础知识
- 2. 論文執筆?投稿?査読 ? ある研究の一生 1. 研究する 2. 論文を書く 3. 論文誌に投稿する 4. 査読される 5. 直して再投稿 6. 査読される 7. 採録 8. 掲載 2 プレスリリース 実用化
- 3. 研究をどうやって公開するか ? Web公開 – 誰でもできる?内容の真偽は不明?誰が見る かわからない ? 本を書く – 売れないと困る?内容については様々 ? プレスリリース – 話題性が必要?専門的な検討は必ずしもない 普通は論文誌掲載と同時かそれ以降 3
- 4. 研究をどうやって公開するか ? 国内会議?査読なし国際会議 – 誰でも発表できる?専門家対象 ? 査読付き国際会議 – 査読は主に件数を絞るため限定的(時間的に も) ? 論文誌(ジャーナル) – 査読あり=内容についてそれなりの整合性? 信頼性があると認められる 4
- 5. 論文執筆 ? 人はなぜ論文を書くのか – 発表しない研究は存在しないのと同じ – ジャーナル論文になっていない研究は十分信 頼されない(ジャーナルに載っても信頼でき るとは限らないが) – 研究が存在した、という証明 – 生活のため 5
- 6. 論文を書くことの目的 ? 最大の目的は 「自分のやった研究は意義がある」 ということを読者に理解させること – 実験結果はそのための「証拠」に過ぎない – 実験結果だけを書いても意義は伝わらない 「解釈」が重要 – 意義が伝わるなら実験結果は不要かもしれな い – その上で、できるだけ内容の詳細な公開 6
- 7. 論文執筆で考慮すべき要素 ● ストーリー ● 内容を可能な限り類型にあわせて語る ● モチベーション ● 「どうやって研究したか」よりも「なぜ研究 したか」の方が大事 ● 見た目 ● わかりやすい文章で書く 7
- 8. 典型的な論文内容の類型 ● 研究背景:問題の定義、従来研究 ● 研究の動機付け:何を解決しようとした のか ● アイデア ● 実現方法 ● 効果 ● まとめ 8
- 9. 例 ● 研究背景 ● 村の裏山には悪い鬼がいて、村人は困っていた ● いままで何人もの勇者が鬼に倒されている – できれば具体例を挙げて ● 研究の動機付け ● 鬼を倒すために、新しい魔法を開発する – 場合によっては今まで開発された魔法の説明 9
- 10. 例 ● アイデア ● 鬼は豆が嫌いなので、豆をかたどった呪符を 使えば退治できるはず ● 実現方法 ● 紙に豆の絵を書いて、念のために急急如律令 とか書いてみた – 評価のときに問題になるパラメータはしっ かり書く – なぜ本物の豆を使わないのか、等の説明 – 「念のため」には意味があるのか説明 10
- 11. 例 ● 効果 ● 豆の絵の呪符と、鳩の絵の呪符の両方 を使って鬼と戦ってみた ● 鳩の絵は効かなかったが、豆の絵は効 いた ● 豆の数は3個がいいようだが、そこで鬼 が死んだのでそれ以上の効果はわから ない ● まとめ ● 新しい魔法を開発した ● 今後はもっと多くの鬼と戦って効果を 検証していきたい Fig. 1 The charm. 11
- 12. モチベーション ● HOWよりもWHY ● なぜその問題に取り組む必要があるのか ● なぜ従来の解決法ではだめなのか ● なぜ提案法を使う必要があるのか – 必然的なのか、ありうる解決法の一つな のか ● なぜこのような実験結果が出たのか 12
- 13. わかりやすく書く ● 提案手法の内容、実験の内容を再整理する ● 実行した順番に書くとわかりにくいことが多い ● 問題提起から結果まで、「言いたいこと」がわき 道にそれないように整理 ● 実験の順序と記述の順序が逆転することもよくあ る ● 用語と記述に気を配る ● 専門用語は読者を考えながら使う ● 数式をうまく使うと説明が簡潔になる 13
- 14. 英文論文の場合 ? 科学論文は英文が主流 – 和文だと日本人以外に読んでもらえない ? 注意点 – 頼むから投稿前にスペルチェックしてくださ い ? 文法チェッカーの利用も効果的 – 可能ならお金を出して英文校閲を受ける ? オンラインの校閲業者もたくさんある ? 音響学会の場合は掲載前に校閲を受ける (経済的補助あり) 14
- 15. 論文を投稿する ? 論文の内容が固まったら – 投稿の覚悟を決める – 論文誌を選ぶ – 体裁を整える – 投稿 – 査読結果への対応 15
- 16. 投稿のための覚悟 ? 論文掲載のためには「査読」を受ける – 「査読される」とは「批判される」というこ と ? 「評価」と「批判」は同じ行為だと理解する ? 内容への批判と自分への批判を切り離す ? 批判を建設的にとらえる – 査読を受けるために必要なのは「勇気」 ? 「査読なんて怖くない」というのは「査読は怖 い」ということ ? 怖さを克服するのが勇気 16
- 17. 論文誌を選ぶ ? どんな論文誌があるか – JASA, IEEE Trans., Acoust. Sci. Tech., Acta Acustica, Applied Acoustics, … – 論文誌によって、論文の体裁だけでなく、用 意すべき情報なども異なる場合がある ? “Highlight”みたいなものを書く雑誌もある ? 選ぶ時のポイント – 分野性、掲載の速さ、難しさ等 – 怪しい論文誌は避けましょう ? 音響学会誌?ASTは伝統あるまともな論文誌です 17
- 18. 体裁を整える ? 内容以外の要素 – タイトル、著者名 ? 著者名は後から変更できないことが多い – 最大ページ数、図表の数 ? ページ数には制限がある場合がほとんど ? 図表の数に制限がある論文誌?原稿種別がある – 引用形式 – 用語、単位など 18
- 19. 査読(ピアレビュー) ? 論文が扱っている分野に近い研究をして いる人が論文を読んで評価する制度 – 学術論文だと編集者だけが読んで価値を理解 するには限界がある – 専門的に見た論文の価値を、専門に近い研究 者の判断に委ねる – 通常2名以上の査読者による査読を受ける – 編集者は査読者の意見を見て論文の扱いを決 める 19
- 20. ? 代表的なポイントは??? – 分野性(論文誌と分野があっているか) – 可読性(了解性)(読んで理解できるか) – 信頼性(内容が信じるに足る証拠があるか) – 新規性(新しい内容が含まれているか) – 有効性(何かの役に立つ内容か) 査読のポイント 必須 どちらかが高い 20
- 21. 査読される時の心構え ? 査読者は「最初の読者」 – 論文で何かを主張して読者にわからせる責任 は著者にある – 査読者は比較的専門が近い研究者なので、そ こに理解されなければ誰にも理解されない 21
- 22. 改訂論文の投稿 ? 条件付き採録になった場合は – 査読者?編集委員の掲載条件に合うよう論文 を改訂 – 「回答文」の作成 ? 掲載条件1つずつにどう対応し、その結果どう論 文を修正したのかを列挙 ? 主張点を明確にし、査読者の負担を軽減する 22
- 23. 再投稿 ? 論文誌によっては、返戻された論文を再 投稿するときに回答文をつけることがで きる – 音響学会はこのような対応 – 前の論文の「続き」として扱われることが多 い – 注目して欲しい部分の明確化 ? 十分推敲しましょう 23
- 24. おわりに ? 皆さんの研究は国際レベルです – 音響学会の研究発表会の内容は、多くの国際 会議と比較しても決して見劣りしない ? その研究成果の多くが埋もれています – 数年後に欧米のどこかで似たようなことを やって論文になって引用されている ? 論文を書くことは社会への貢献です – 自分の研究した内容を、誰もがわかる形で公 表して、知識を共有する 24