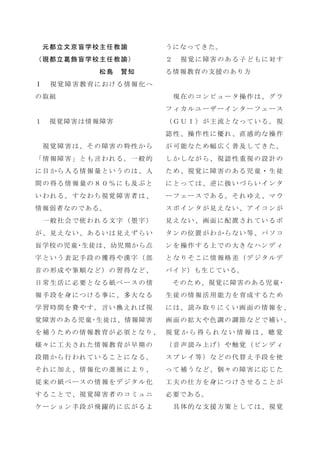8
- 1. 元都立文京盲学校主任教諭 うになってきた。 (現都立葛飾盲学校主任教諭) 2 視覚に障害のある子どもに対す 松島 賢知 る情報教育の支援のあり方 Ⅰ 視覚障害教育における情報化へ の取組 現在のコンピュータ操作は、グラ フィカルユーザーインターフェース 1 視覚障害は情報障害 (GUI)が主流となっている。視 認性、操作性に優れ、直感的な操作 視覚障害は、その障害の特性から が可能なため幅広く普及してきた。 「情報障害」とも言われる。一般的 しかしながら、視認性重視の設計の に目から入る情報量というのは、人 ため、視覚に障害のある児童?生徒 間の得る情報量の80%にも及ぶと にとっては、逆に扱いづらいインタ いわれる。すなわち視覚障害者は、 ーフェースであ る。それゆえ、マウ 情報弱者なのである。 スポインタが見えない、アイコンが 一般社会で使われる文字(墨字) 見えない、画面に配置されているボ が、見えない、あるいは見えずらい タンの位置がわからない等、パソコ 盲学校の児童?生徒は、幼児期から点 ンを操作する上での大きなハンディ 字という表記手段の獲得や漢字(部 となりそこに情報格差(デジタルデ 首の形成や筆順など)の習得など、 バイド)も生じている。 日常生活に必要となる紙ベース の情 そのため、視覚に障害のある児童? 報手段を身につける事に、多大なる 生徒の情報活用能力を育成するため 学習時間を費やす。言い換えれば視 には、読み取りにくい画面の情報を、 覚障害のある児童?生徒は、情報障害 画面の拡大や色調の調節などで補い、 を補うための情報教育が必須となり、 視 覚 か ら 得 ら れ な い 情 報 は 、 聴 覚 様々に工夫された情報教育が早期の (音声読み上げ)や触覚(ピンディ 段階から行われていることにな る。 スプレイ等)などの代替え手段を使 それに加え、情報化の進展により、 って補うなど、個々の障害に応じた 従来の紙ベースの情報をデジタル化 工夫の仕方を身につけさせることが することで、視覚障害者のコミュニ 必要である。 ケーション手段が飛躍的に広がるよ 具体的な支援方策としては、視覚
- 2. 的な画面情报が全く入手できない 率も高くなり、携帯電話やコンピュ (全盲)場合には、オペーレーティ ータにまつわる様々な犯罪を知り、 ングシステム(OS)やアプリケー 情報弱者として情報犯罪から自分の ションの情報を、音声リーダーで読 身を守る工夫を、主体的に行う姿勢 み上げさせ聴覚情報として入手した を身につけさせることも大切である。 り、ピンディスプレイなどに出力し それらの結果、教室で学ぶことだ 一過性の音声に対してフィードバッ けでは得られない多くの情報に、よ クできる触覚情報として入手する方 り能動的にリアルタイムに接するこ 法がある。 とができるようになる。このように、 また、文字データをデジタル化す 適切な支援機器の工夫と情報教育に ることで、点字と普通文字等との相 より、視覚障害教育においては情報 互変換を行うことができ、点字利用 活用能力を伸ばすことが、情報格差 者でも漢字カナ混じりの文章を書き、 の幅を狭め、情報化社会への参画す 印刷することができる。一方、画面 る態度を育てることにつながる。 が読みとりにくい(弱視)場合には、 ( 参 考 文 献 教育の情報化??文科 その視覚特性に合わせて、画面の拡 省) 大?白黒反転?色の調節?音声化な どを行なう。どちらにおいても、マ Ⅱ 視覚障害教育における実践 ウスが使えない、キーボードがうま く操作できないなどの現象に対応す 盲学校等においては、視覚からの るために、マウス操作をキーボード 情報の不利を補う手段として、音声 で操作するためのキーの割り当て 読み上げの技術を追求し、マウス操 (ショートカット)を覚える必要が 作に頼らなくともコンピュータの操 ある。 作ができるような工夫を積み重ねて また、情報化の進展が視覚障害者 きた。また、画面情報をピンディス の生活に新しい可能性を切り開いて プレイに表示することで、触覚によ くれる反面、情報化社会が自己の生 り情報を得ることができ、それらの 活環境にどのような影響を与えてい 機器の発達により得られる情報量も るかを、適切に把握?理解させなけ 増えてきた。 ればならない。近年携帯電話の所持 一方、画面が見づらい弱視の場合
- 3. に は 、 音 声 読 み 上 げ の 技 術 に 加 え て 、 められる。 弱視者用の多機能な専用ソフトウェ アを活用することにより操作性が向 Ⅲ 実践事例 上し、情報機器の活用の幅を広げて きた。 1 盲学校における、音声リーダー 文字処理においては、コンピュー の活用と音声対応ソフトによるネッ タ点訳の技術が進歩し、文字をデジ ト検索(高等部 情報A) タル化することで飛躍的に点訳の労 力 を 省 く こ と が で き る よ う に な っ た 。 〈ねらい〉 また、音声リーダーの辞書機能の向 ①校内ネットワークと階層構造の理 上により、点字利用者が普通文字の 解 文章を同音異句を遣い分けながら、 ②視覚特性に合わせた画面設定と音 手軽に書くことができるようになっ 声リーダーを用いたワープロソ フト た。さらに、紙に印刷された普通文 の操作 字をスキャナーで取り込みOCRに ③長文の要約と音声リーダーを用い かけてデジタル化することで、音声 た漢字カナ混じり文の表記 化したり点字化したりと出力形態を ④音声対応ソフトによる、インター 簡単に変化させることができるなど、 ネット上の辞書?ニュース?路線等 文字のデジタル化により取り扱える の検索 情報量が格段に増加した。 このように、個々の障害の実態に応 〈学習の展開〉 じた適切なアシスティブ?テクノロ 音声リーダーとキーボードのショ ジーを講じることで、視覚に障害の ートカットを利用し、ネットワーク ある児童?生徒が一般社会と情報を ハードディスクのフォルダー内にあ 共有することが、幅広くできるよう る問題文にアクセスし開く。その際、 になってきた。それ故に、情報機器 自身の障害特性に合わせた音声設定 の活用は、コミュニケーション手段 と文字サイズ設定?ハイコントラス を飛躍的に広げ、デジタルデバイド ト(白黒反転)設定を適宜行う。長 を減少させるために必須であり、情 文の社会ニュース(問題文)を音声 報活用能力を伸ばすことが大いに求 リーダーで読み上げさせ、内容を要
- 4. 约してワープロソフトでまとめる。 能的負担を軽減し、さらに は操作性 また、点字利用者にはピンディス プ も向上することを体験する。音声リ レイを併用させる。ショートカット ーダーを用いることで、印刷物では の利用により、ソフトウェアの切り 枚数も多くなり生徒にとっては読む 替えやアプリケーションの操作等が 気力が下がってしまうような文章量 素早く的確に行え、操作性が向上す でも、比較的楽に読み進むことがで る感覚を体験させる。 きる。 問題文に関するニュースや解らな また、点字利用者にはピンディス い語句、地域等を音声対応ソフトを プレイを併用させることで、一過性 用いてネット検索し、それぞれまと な音声情報だけではなく、 画面情報 める。 を触覚情報に変換させフィードバッ 要約をもとにそれぞれの感想を報 クしながらの繰 り返しの操作が可能 告しあい、ネット検索で調べた関連 になり、情報処理能力が向上する。 記事及び関連事項等を報告する。 音声対応ネット検索ソフトを用いて、 リアルタイムにニュース検索ができ 〈機器の工夫〉 ること、また、ネット上の辞書を利 ①マウスレスを基本としたショート 用することにより、書籍としての辞 カットの利用 書より素早く語句検索ができること ②音声リーダー及び音声対応ネット を体験する。 検索ソフト(辞書?ニュース?路線 教材?教具として音声リーダーや 等)の利用 ピンディスプレイ等に頼りがちだが、 ③弱視者用画面設定ソフトの利用 それだけではパソコン特有のディレ ④ピンディスプレイ等の触察機器の クトリ等の階層構造やファイル保存 利用 の際の処理の流れなど、現在コン ピ ⑤画面をデフォルメした立体コピー ュタの画面上がどのように表示され、 の工夫 どのように移動しているかといった 内容を知ることは難しい。そこで、 〈ポイント〉 画面をデフォルメした立体コピーを マウスレスを基本にし、音声とシ 用意し、触察によるイメージ化を図 ョートカットを利用することで 視機 る。(図1)
- 5. (东京都立文京盲学校 高等部 情報A 平成二一年度実践 よ り) 図1 階層 構 造を 表 した 立 体コ ピ ー 上記一連の操作を統合的に行うこ とで、情報の享受に関しては受け身 であった視覚に障害のある児童?生 徒たちに、能動的に情報を集め取り 扱う姿勢を身につけさせることが大 切である。 「できないから使わない」ではな く、「どのようにしたら、活用できる か」と、知的好奇心を持って情報機 器に向かう力をつけさせる。この観 点が、視覚障害教育における情報教 育の大きな柱になる。