1. Toshihiro Ichitani All Rights Reserved.
Ichitani Toshihiro
市?聡啓
Photo credit: Israel Defense Forces on Visualhunt.com / CC BY-NC
「アジャイル ブリゲード」
対?する?項を組織の構造と仕組みによって繋ぐ
2. 市? 聡啓
Ichitani Toshihiro
開発会社 (エンジニア) → SIer (プロマネ)
→ プラットフォーマー (プロデューサー)
→ 起業 (仮説検証型アジャイル開発)
→ 伴?する変??援者
Since 2001
特に専?は
?仮説検証 (サービスデザイン)
?アジャイル開発
4. Toshihiro Ichitani All Rights Reserved.
ぼくらのチーム?ジャーニー
?越境するプロダクト開発の現場?
なぜ戦略と現場活動が?致しないのか
─「現在指向バイアス」を超え、
? DXを推進するCoEとCDOの役割
https://note.com/papanda0806 https://twitter.com/papanda
7. DX is a rede
fi
ne
of UX
外部環境の変化
テクノロジーを活?した
新しいサービス?
事業の創出
顧客体験の再定義
11. Photo on Visual hunt
「?休さんの屏?のトラ」DX
?周?のDXは、「?休さんの屏?のトラ」で失敗に終わる
(1)“DX戦略” が実?に繋がらない
??密度の?い絵とロードマップはあるが、それを実?に
??移す体制?運営(=“作戦”)が存在しない
??(外部?援者に「お絵かき」だけされて逃げられている)
(2)DXプロジェクトを?ち上げるが遂?で失敗する
??プロジェクトまでは?ち上げるが、狙いも作戦も弱く
??(?ぶらで始める)、「とにかく最初に?てた?針を
??達成する」が?的となり、次に繋がることがない失敗
??へと?る。
12. Photo credit: Richard Walker Photography on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND
探索的な取り組みにおける
最?の失敗とは
何も学べていないこと
13. Photo credit: The Library of Congress on Visualhunt / No known copyright restrictions
DXで直?する
困難の本質とは何か?
15. Photo credit: aka Quique on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND
分断
変?への果敢な取り組みが
際?たせるもの、それは
「これまで」と「これから」
「既存事業」と「新規事業」
「全体」と「詳細」
「経営」と「現場」
「役割」「職位」「職能」「世代」
16. Photo credit: tiseb on Visual Hunt / CC BY
組織の中に組織をつくる
(“出島” 戦略による意図的な組織分断)
「これまで」の影響から隔離し、
「これから」に向けた「実験場」を創り出す
主たる狙いは「評価?法」の刷新 (失敗を許容する)
KGI/KPIを既存事業や組織の「これまで」から?線画す
ことで?動きを取れるようにする
18. Photo credit: akahawkeyefan on Visualhunt.com / CC BY-NC-SA
“出島” だけでは
組織はトランスフォームしない
まともな評価と実験環境の確保、新しいケイパビリティ
獲得の為の戦略として「出島」必要だが
”本?” (既存) 側の変?が置き去りになるままでは
組織全体の成果までは到達できない
22. Photo credit: aka Quique on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND
繋ぐ
概念と役割、組織それぞれの
独?性を保ちながら、
「全体」と「詳細」の「同期」
「経営」と「現場」の「?致」
「既存事業」と「新規事業」の「協働」
(統合しない、排斥しない、更新対象にしない)
24. Photo credit: aka Quique on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND
DX2周?にあたり向き合うべき分断
?全体と詳細の「不同」問題
?経営と現場の「不?致」問題
?既存事業と新規事業の「不協和」問題
32. Photo on Visual hunt
CoEを外部に丸ごと任せる…絶対にヤメル
良くわからないので、
CoEをほぼ丸ごと外部の指?のもと作る、
あるいは、外部に丸ごと預けてしまう
?根っこを外部に渡すようなもの。
「?休さんの屏?のトラ」DXへまっしぐら
36. Photo credit: Israel Defense Forces on Visual hunt / CC BY-NC
アジャイル ブリゲード
両利きのチーム + アジャイルな運営
対?する?項を組織の構造と仕組みによって繋ぐ
38. to credit: Israel Defense Forces on Visual hunt / CC BY-NC
内部と外部の専??材で混成チームを?ち上げる
アジャイル ブリゲードの構成
全社課題
バックログ
(DX戦略)
アジャイル ブリゲード
経営?材
(CDO)
ミドル 現場 領域A
専??材
領域B
専??材
段階と断?に
よるマネジメント
新規事業への
専?性提供
既存事業への
専?性提供
(全体と詳細の同期) (新規と既存の協働)
(経営と現場の?致) ?必要で不?する専?性は外部
?から取り込む
?- 仮説検証
?- プロダクトマネジメント
?- アジャイル開発
?- クラウド / IoT / AI /BC etc
?運営の舵取りは内部?材が
?コミットしてあたる
?※ただし運営?体がアジャイルな為
??適切な専??材とともに取り組む
42. Photo credit: domesticat on VisualHunt.com / CC BY-NC-SA
つまり、その場にいるチーム、関係者のうち
?場役割を越えて、「狙い」をあわせられる
?々で、?さく始める
(どこからか救世主がやってくるのを待つ…のではなく)
45. Photo credit: lensnmatter on VisualHunt.com / CC BY-SA
ブリッツ?トラスト
組織内で信頼を得るためには? 結果を出すこと!
つまり、「最初の結果」を出すことに全集中する。
「結果」が、組織内の「次の期待」を連れてきてくれる。
次の取り組みがやりやすくなる(体制をつくることも)
全集中とは? ?時的に持続可能性を無視してでも取り組む。
最初から、持続的な活動をイメージすると、
「セオリーどおりにやろう(スクラムとしては?)」
「無理しても続かないので、可能な選択肢を選ぶ」になる。
これでは、短期間で明確な結果を出すのが難しい。
「?旦ブレーキを壊す」イメージ。それゆえに区切らないと
持たない。
46. Toshihiro Ichitani All Rights Reserved.
越境
Photo credit: James Marvin Phelps via Visualhunt.com / CC BY-NC
組織を越えること、これまでに囚われないこと
47. Photo credit: lensnmatter on VisualHunt.com / CC BY-SA
「ともに取り組む」ことで
新たな「WHY」「HOW」が伝播する
新たな「WHY」
?不確実な状況に取り組む際のスタイルとして「探索」
?正解が無い = ?分たち??で問い続けるしかない
?「われわれはなぜここにいるのか?」「われわれは何者なのか?」
?「正しいものを正しくつくれているか?」
新たな「HOW」
?仮説検証型アジャイル開発をともに辿ることで学ぶ
?状況によっては「チーム開発」「仕事のやり?のモダン化」から
ともに取り組むとは、同じ?向をともに?ているということ
48. Photo credit: The Library of Congress on Visualhunt / No known copyright restrictions
実際
55. Toshihiro Ichitani All Rights Reserved.
Photo credit: Israel Defense Forces on Visualhunt.com / CC BY-NC
?企業、地域企業、そして国における
トランスフォーメーションは
2周?のこれからが勝負のトラック
57. Photo on Visual hunt
?企業、伝統的な組織ほど求められる
変?の「求??」
多くの?々が変?の?向性をあわせながら進むには
ハコ(組織)さえあれば良いわけではない。
中?(?)は変わっていないのだから。
迷わず活動を続けるための「?印」がいる。すなわち求??。
では、求??とは?
カリスマの存在?(いるの?)
??化?(いますぐ?)
?ルール?(まさか!)?
61. Photo credit: [-ChristiaN-] on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND
プロダクトファーストで
組織変?を牽引する
「顧客体験を変えるためのプロダクト作り」
だけではなく
「?分たち??を変えるためのプロダクト作り」へ

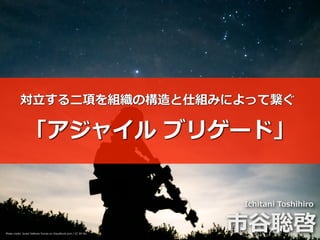



























































![Photo credit: [-ChristiaN-] on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND
プロダクトファーストで
組織変?を牽引する
「顧客体験を変えるためのプロダクト作り」
だけではなく
「?分たち??を変えるためのプロダクト作り」へ](https://image.slidesharecdn.com/agilebrigade-210219124434/85/-61-320.jpg)



![プロダクトを作り、世に問おう。
Photo credit: [-ChristiaN-] on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND](https://image.slidesharecdn.com/agilebrigade-210219124434/85/-65-320.jpg)





