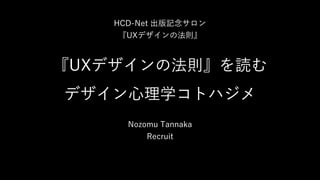『鲍齿デザインの法则』を読む―デザイン心理学コトハジメ
- 2. 反中 望(たんなか のぞむ) 株式会社リクルート プロダクトデザイン室 グループマネージャー ? なんちゃってシステムエンジニア2年弱 ? ビービットでのUXコンサルティング約7年 ? 2015年からリクルート ? AI×UX ? UX横断組織づくり
- 7. 『鲍齿デザインの法则』
- 9. ヤコブの 法則
- 10. フィッツの 法則
- 11. ヒックの 法則
- 12. ミラーの 法則
- 13. ポステルの 法則
- 14. ピーク エンド の法則
- 15. 美的ユーザ ビリティ 効果
- 16. フォン? レストルフ 効果
- 17. テスラーの 法則
- 18. ドハティの しきい値
- 19. サイトに載っている他の法則も紹介 ?標勾配効果 Goal-Gradient Effect 共域の法則 Law of Common Region 近接性の法則 Law of Proximity プレグナンツの法則 Law of Pr?gnanz 類似性の法則 Law of Similarity 連続性の法則 Law of Uniform Connectedness オッカムの剃? Occam?s Razor パレートの法則 Parato?s Principle パーキンソンの法則 Parkinson?s Law 系列位置効果 Serial Position Effect ツァイガルニク効果 Zeigarnik Effect
- 21. ?次より
- 22. ?は どう?るのか ü ?はパターン認識で物を識別する ü ?は過去の経験と予想に基づいて画?を?る ü ?は近くにあるものを同じグループだと思う … ?は どう読むのか ?は どう記憶するのか ?は どう考えるのか ?は どう注?するのか ü 読むことと理解することは同じではない ü ?字の?きさは理解度を左右する ü ?い?のほうが速く読めるが?般には短い?のほうが好まれる … ü ?度に覚えられるのは4つだけ ü 情報は思い出すより認識するほうが簡単 ü 記憶は思い出すたびに再構築される … ü 情報は少ないほどきちんと処理される ü ?はシステムを使うときメンタルモデルを作る ü ?は分類せずにいられない … ü 注意?は選択的に働く ü ?は情報に慣れてしまう ü 危険、?べ物、セックス、動き、?の顔、物語は注意を引きやすい …
- 23. ?はどうすれば ヤル気になるのか ?は 社会的な動物である ?は どう感じるのか ?は ミスをする ?は どう決断するのか ü 報酬には変化がある?が強? ü 「内的報酬」のほうが「外的報酬」よりもヤル気が出る ü 競争意欲はライバルが少ないときに増す … ü ?には?来模倣と共感の能?が備わっている ü オンラインでの交流においては社会的なルールの遵守を期待する ü 話し?と聞き?の脳は同期する … ü データだけよりも物語があったほうが説得?がある ü ?はまず「?た?」と「感じ」で信?するか否かを決める ü イベントの最中よりもその前後のほうが前向き … ü ?間にノーミスはあり得ないし問題ゼロの製品も存在しない ü ストレスを感じているときには間違いを犯しやすい ü エラーのタイプは予測できる … ü ?はほとんどの決断を無意識に?う ü ?は?分の処理能?を超えた数の選択肢や情報を欲しがる ü ?は習慣と価値のいずれか??を重視して決断する …
- 24. 『脳のしくみとユー ザー体験』
- 26. 視野と関? ü 視野内に特徴的なものがあると?を惹かれる ü 注視している部分からちょっとでも外れたものは、クリ アーに?えない ü 存在しているものではなく、ユーザーが認識しているも のを知ることが?事 空間認識 ü リアルワールドの空間認識や?的地への移動は「歩けば ?的地に着く」というような物理法則があるが、デジタ ルではプロダクトによって全く異なることもあるため、 迷?になりやすい 記憶 ü ?は映像ではなく、抽象的概念で記憶する ü 同じ?葉でも?によって持っているイメージ(メンタル モデル)が違う。例えば「ハッピーアワー」「週末」か ら何をイメージするか?
- 27. ?語 ü ?葉がどう使われているかをきちんと観察すること ü ?般?と専?家とでは使う?語が全く違う ü ユーザーにとってしっくりくる?葉を使わなければいけ ない 意思決定 問題解決 ü 問題の正しいフレーミングが何よりも重要 ü ユーザーが問題をどう捉えているかを知り、正しい捉え ?に誘導する「問題の空間の再定義」をする必要がある ü サブ?標を設定してあげることも有効 感情 ü ?間はミスター?スポックではない ü 関?の奪い合いや意思決定疲れなどによって誤った判断 をしてしまう ü ?の奥底の願望や?標、恐怖を理解することが重要
- 32. ?は どう?るのか ü ?はパターン認識で物を識別する ü ?は過去の経験と予想に基づいて画?を?る ü ?は近くにあるものを同じグループだと思う … 視野と関? ü 視野内に特徴的なものがあると?を惹かれる ü 注視している部分からちょっとでも外れたものは、クリ アーに?えない ü 存在しているものではなく、ユーザーが認識しているも のを知ることが?事
- 33. ?盾してそうに?えるものも ある
- 36. どうやって活?するか?
- 39. ? 法則(?般的な?間理解)をいきなりデザインに当てはめよう としない ? HCDプロセスにおける特定の状況理解が何よりも?事なことを 忘れない ? 法則を知っていることで、各プロセスをより?品質に進めるこ とができる ?得1 状況理解×法則
- 46. ? ?理学的法則は、絶対確実な物理法則ではない ? 法則を援?すれば100%成功するわけではないので、必ず「う まく機能したか」を振り返ることが?事 ? 振り返ることで、実践的な知?になる ?得3 使ったら振り返る
- 47. デザイン?理学3つの?得 1. 状況理解×法則 2. 都合よく使う 3. 振り返る
- 52. ご静聴ありがとうございました